予防接種と子供の健康
▼予防接種を受けましょう▼
お母さんから赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、生後3か月を過ぎると自然に失われていきます。この時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要がでてきます。
これに役立つのが予防接種です。
予防接種の大切な目的には、
1.自分がかからないために
2.もしかかっても症状が軽くてすむために
3.まわりの人にうつさないために
があげられます。
子どもの発育とともに外出の機会が多くなります。保育園や幼稚園に入るまでには積極的に予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように予防しましょう。
ページ上部へ▲
▼予防接種(ワクチン)とは▼
はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルス、細菌、または菌の産生する毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを、予防接種といいます。「予防接種」に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
感染症を予防するのに、もっとも安全で確実性の高い方法がワクチン接種です。ワクチンを接種することで、子どもたちを病気から守ることができます。
ワクチンで防げる病気はワクチンで予防しましょう。定期予防接種の種類や対象年齢については以下のサイトをご覧ください。

ページ上部へ▲
▼予防接種の接種間隔▼
予防接種の接種間隔はそれぞれ定められています。最近は必要に応じて同時接種も行われるようになってきました。かかりつけの先生と相談し、積極的に予防接種を受けましょう。
▼富山県内定期予防接種広域化▼
市町村が実施する小児を対象とした定期予防接種について、富山県と富山県医師会並びに各市町村で調整を重ね、平成22年6月1日から居住地に関わらず県内全域の協力医療機関で接種ができるようになりました。
ページ上部へ▲
▼任意予防接種(自費)の種類▼
おたふくかぜ・水ぼうそう・ロタウイルス・B型肝炎・インフルエンザなどがあります。
ページ上部へ▲
▼予防接種を受ける前に▼
(1)一般的注意
予防接種は健康な人が元気な時に接種を受け、その病原体の感染を予防するものですから、体調の良い時に受けるのが原則です。日ごろから保護者の皆さんは子どもの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。そして何か気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけの先生や保健センター、市町村担当課にご相談ください。
以下の注意を守って、安全に予防接種を受けましょう。
①受ける予定の予防接種について、通知やパンフレットをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解し ましょう。わからないことは接種を受ける前に質問しましょう。
②受ける前日は入浴(又はシャワー)をさせ、体を清潔にしましょう。
③当日は朝から子どもの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認してください。接種に 連れていく予定をしていても、体調が悪いと思ったら、やめる勇気をもちましょう。
④清潔な着衣をつけさせましょう。
⑤接種を受ける子どもの日ごろの状態をよく知っている保護者の方が連れていきましょう。
⑥予診票は子どもを診て接種をしてくださるお医者さんの大切な情報です。責任をもって記入するようにし ましょう。
⑦母子健康手帳は必ず持っていきましょう。
(2)予防接種を受けることができない人
①明らかに発熱のある人
一般的に熱のある人は、接種場所で測定した体温が37.5℃を超える場合をさします。
②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
急性の病気で薬をのむ必要のある人は、その後の病気の変化もわかりませんので、その日は見合わせるのが原則です。
③その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こすことのある人
「アナフィラキシー」というのは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、ショック状態になるような激しい全身反応のことです。
④ポリオ、麻しん(はしか)、風しんでは妊娠していることが明らかな人
子どもには直接関係ない規則ですが、任意で受ける人のことも考慮したものです。
⑤その他、医師が不適当な状態と判断した場合
上記の①~④に入らなくても医師が接種不適当と判断した場合には接種できません。
(3)予防接種を受けるに際し、お医者さんとよく相談しなければならない人
次に該当すると思われる人は、主治医の先生がいる場合には必ず前もって診ていただき、その先生の所で接種してもらうか、あるいは診断書又は意見書をもらってからいきましょう。
①心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などで治療を受けている人
②発育が悪く、お医者さんや保健婦の指導を継続して受けている人
③未熟児で生まれて発育の悪い人
④カゼなどのひき始めと思われる人。こういう時は体の状態がはっきりするまで、なるべくやめましょう。
⑤前に予防接種を受けた時に、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどのアレルギーを思わす異常がみられた人
⑥薬の投与を受けて皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことのある人
⑦今までにけいれんを起こしたことがある人
けいれんの起こった年齢、そのとき熱があったか、熱がなかったか、その後おこっているか、受けるワクチンの種類は何かなどで条件が異なります。必ずかかりつけの先生と事前によく相談しましょう。
原因がはっきりしている場合には、一定期間たてば接種できます。
⑧過去に中耳炎や肺炎などによくかかり、免疫状態を検査して異常を指摘されたことのある人
⑨ワクチンには抗原のほかに培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っていますので、これらにアレルギーがあると言われたことのある人
⑩家族の中で、または遊び友達、クラスメートの間に、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)などの病気が流行している時で、予防接種を受ける本人がその病気にかかっていない人
(4)予防接種を受けた後の一般的注意事項
①予防接種を受けたあと30分間は接種会場で子どもの様子を観察するか、先生とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
②接種後、生ワクチンでは2~3週間、不活化ワクチンでは24時間は副反応の出現に注意しましょう。
③入浴は差し支えありませんが、わざと注射した部位をこすることはやめましょう。
④接種当日はいつも通りの生活をしましょう。はげしい運動は避けましょう。
以上の注意をよく読んで、分からないことがあれば質問しましょう。
ページ上部へ▲
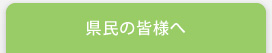
![]()















