流行性の疾患を集めてみました、少しでもお母さんに役立てばと思っております。
▼1.麻しん(はしか)▼
麻しんウイルスで起きる伝染性の強い病気で、 免疫のない人が感染すると、 ほとんどが発病します。
10~12日の潜伏期(病気をもらってから発病するまでの期間)の後、 まず、せき、鼻みず等のかぜ症状から39~40℃にも及ぶ発熱が3~4日続きます。
この熱はいったん下がりますが、再び発熱がみられ、 これと共に発疹(ほっしん)が全身に表れます。
5~6日後、発疹はでてきた順序で消退してゆき、 あとに褐色の色素沈着を残します。
また、はしかには「コプリック斑」 と呼ばれる斑点がほおの内側(口腔粘膜)に出現する特徴もあります。
ときに肺炎、中耳炎、脳炎等の合併症を起こすこともありますので、 十分な注意が必要です。
予防接種が有効です。1歳になったらできるだけ早く接種しましょう。
ページ上部へ▲
▼2.風しん▼
風しんウイルスに感染して起きる病気で、軽い麻疹の症状に似ています。
2~3週間の潜伏期の後、発熱と共に発疹がみられ、3日間程持続しますが、熱のでないこともあります。また、この時期に首や耳の後ろのリンパ節の腫れる症状が現れることも特徴です。
妊婦さんが妊娠初期にこの病気にかかると、心臓の奇形や白内障などの子供 (先天性風疹症候群といいます)が生まれる危険性が高くなります。このため、この病気に対する抗体のない女性は、妊娠前に風しんの予防接種を受けることをお勧めします。また、抗体のない妊婦さんは、風しん患者と接触しない等、特に感染予防を心掛けるようにして下さい。
ページ上部へ▲
▼3.水痘(みずぼうそう)▼
水疱(すいほう)性の発疹がでる病気で、水痘・帯状疱疹ウイルスの感染によっておこります。
2~3週間の潜伏期間ののち、発熱と共に発疹が現れます。個々の発疹は数時間のうちに紅斑、丘疹、水疱となり、やがては痂皮(かさぶた)になって脱落します。
からだの中に入ったウイルスは水痘発疹が消えた後も神経節細胞の中に長い間潜んでいて、からだの抵抗力が低下すると帯状疱疹になることがあります。
かさぶたになるまでは感染力(うつす力)があります。
ページ上部へ▲
▼4.流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ▼
ムンプスウイルスに感染して起きる病気で、発熱と耳の下(耳下腺)の腫れが特徴です。
潜伏期は3週間前後で、耳下腺の腫れのほかに、あごの下(顎下腺)や首のリンパ腺の腫れ、睾丸炎、膵炎、髄膜炎などの合併症が知られています。このため、決して軽い病気と軽視することはできません。
耳下腺の腫れは3~7日でなくなり、一度感染すると終生免疫が得られます。腫れが引くまでは感染力があります。
ページ上部へ▲
▼5.百日せき▼
百日せき菌に感染して起きる病気で、顔を真っ赤にしてせき込んだ後、 一気に息をヒューと吸い込む特徴のあるせきをします。
潜伏期は7~10日位で、普通は熱がでません。乳児では特に重篤になりやすく、しばしば肺炎、脳症などを併発するので、早期診断、予防が重要になります。
三種混合で予防できますので、3か月以降できるだけ早くに接種しましょう。
ページ上部へ▲
▼6.溶連菌感染症▼
溶血性レンサ球菌によって起こる「風邪」に似た病気で、猩紅熱はこの菌で起きる病気の一種です。
A群溶連菌によって起こり、潜伏期は2~4日、舌はいちごのようにザラザラして赤くなり、扁桃も赤く腫れるのでのどを痛がります。時には全身に発疹がみられることもあり、発疹が消えると後は米ぬかのように落ちていきます。
不十分な治療をすると2~3週間後に急性腎炎を起こすことがありますので、お医者さんの指示どおりにきちんと薬を服用して下さい。
ページ上部へ▲
▼7.異型肺炎▼
異型肺炎の病原体は、マイコプラズマ、クラミジア(オーム病) などがあげられますが、この大部分はマイコプラズマの感染によるマイコプラズマ肺炎と考えられております。
7~14日の潜伏期の後、早い時期から咳が症状として認められます。比較的元気ですが通常の服薬で咳と熱が続く時に疑われます。
以前は4年周期で大流行を認めましたが、最近は散発的に流行が認められています。
ページ上部へ▲
▼8.感染症胃腸炎▼
ウイルス又は細菌を原因とした胃腸炎を一括したものであり、いわゆる「お腹にくる風邪」もこの病気に含まれています。
ウイルスの代表的なものとしては、ロタウイルス、ノロウイルス等がありますが、後者は牡蠣(かき)等の食品を介して感染することも知られています。また、細菌性のものとしては、サルモネラ、カンピロバクター、エルシニア、病原性大腸菌、腸炎ビブリオ等によるものが知られています。
脱水を防ぐため、水分摂取が重要です。
ページ上部へ▲
▼9.乳児嘔吐下痢症▼
晩秋から冬にかけて、乳幼児、特に6ヶ月から18ヶ月くらいの赤ちゃんがかかる病気で、嘔吐(おうと)と下痢のみられることが特徴です。
従来、仮性小児コレラ、白色便性下痢症、白痢等と呼ばれていたものがこれに相当し、病気の原因はロタウイルスによるものが大部分とみられております。この病気は下痢による脱水症状を起こしやすいので、十分な水分補給が必要になります。しかし、水分ならば何でも良いというものではありません。ジュース、炭酸飲料等は避け、下痢のひどい時には特に赤ちゃん用のイオン飲料での補給を心がけて下さい。また、下痢でおしりがただれやすくなりますので、よくふき取るようにもしてあげて下さい。
ページ上部へ▲
▼10.手足口病▼
夏に見られる病気で、病名のとおり、手(手のひら)や足(足の裏)や口(口のなかの粘膜)に水疱ができます。
この病気の原因は、主としてコクサッキーウイルスA16型、エンテロウイルス71型で、潜伏期は3~6日といわれています。口の中に発疹のできている時は痛みで食事のできないこともあります。刺激の少ない食品を選んであげるように心がけ、少なくとも水分は十分に補給するようにしてあげて下さい。
ページ上部へ▲
▼11.伝染性紅斑(りんご病)▼
ヒトパルボウイルスB19型によって起こる病気で、潜伏期は4~20日といわれています。
この病気は両頬に蝶の形の赤い発疹ができる特徴があり、このため、俗に「りんご病」「りんごほっぺ病」などと呼ばれています。また、顔の発疹に次いで、手足の伸びる側に網の目状(レース状) の赤い発疹が見られることも特徴です。
合併症としてはまれに関節炎、脳症、溶血性貧血が、また、妊婦さんが感染すると流死産、胎児水腫などを起こすことが知られています。
ページ上部へ▲
▼12.突発性発しん▼
ヒトヘルペスウイルス6で起こる急性の発疹性の病気。患者の多くは1歳未満(特に6~12ヶ月)の乳児で、突発の高熱(38~40℃)で発症します。この時、けいれんや下痢を伴うこともありますが、通常、咳・鼻汁などのかぜ症状は認めません。さらに、発熱の状態が3日位続き、解熱と共に全身に粟粒(あわつぶ)大の赤い発疹が現れますが、この発疹は3~4日位できれいに消えてしまいます。
生まれて初めての発熱の時が多くびっくりしますが、熱が高くても比較的元気は保たれていることが多いです。
ページ上部へ▲
▼13.ヘルパンギーナ▼
コクサッキーウイルスA群が原因で起こる夏かぜの一種で、病気は発熱、喉の痛み、食欲不振などで始まります。
この病気の特徴は口の中や喉に小水疱ができることで、後に小さな潰瘍(ただれ)を形成することもあります。手足口病と同様に口の中に発疹のできている時は痛みで食事ができなくなることもありますので、刺激の少ない食品を選んであげるように心がけて下さい。食べられなくても水分だけは少しずつ細かく与えてください。
数日で治りますが、稀に髄膜炎を併発することもありますので注意して下さい。
ページ上部へ▲
▼14.インフルエンザ▼
インフルエンザウイルスによって起こる病気で、咳、咽頭痛(のどの痛み)等の上気道症状に加えて悪寒(さむけ)、 発熱、頭痛、筋肉痛、倦怠感、食欲不振等の強い全身症状のみられることが特徴です。さらに短期間で、しかも速やかに流行が拡がるため、小中学生を中心とする小児の患者では、しばしば学級閉鎖の状態も報告されています。
また、他に病気を持った老人では肺炎などの合併症を起こし、重篤となる例も報告されていることから重要視されています。インフルエンザウイルスにはA型、B型と呼ぶ二つの型があります。A型はさらにウイルスの性質からAソ連型、A香港型に分類されます。このため、インフルエンザのワクチンは次のシーズンに流行しそうなAソ連型、 A香港型、B型のウイルス株を予想してつくられています。
ページ上部へ▲
▼15.MCLS(川崎病)▼
この病気は発見者(川崎富作先生)の名前にちなんでこのように呼ばれていますが、乳幼児に好発し、原因はまだはっきりしていません。
特徴的な症状は、①5日以上続く発熱、②口唇の紅潮、眼球結膜(白目の部分)の充血、③型が不定な発疹、④顎部(くびの部分)などのリンパ節の腫れ、⑤硬性浮腫(さわると硬さのあるむくみ)、⑥指先から皮膚が薄くはがれ落ちるなどがあり、このうち発熱を含む5症状があれば診断することができます。
また、この病気の合併症として、冠動脈(心臓に酸素や栄養素を運ぶ血管)の病変が知られています。これは、急性期が過ぎるとともに軽快するものもありますが、冠動脈瘤(血管にできたコブ)や拡張を残し、突然死を起こす場合もあります。このため、症例によっては冠動脈バイバス手術の適応となることもあります。
ページ上部へ▲
▼16.咽頭結膜熱(プール熱)▼
アデノウイルスの感染によって起こり、発熱、咽頭炎などの風邪様症状と共に結膜炎を伴います。また、夏期に多発し、しばしば汚染されたプールの水を介して感染するため、別名「プール熱」とも呼ばれています。
通常は5~7日の潜伏期の後、3~4日熱が続いて治ります。最近のわが国では、アデノウイルス3型、4型、19型によるものが多くみられています。
ページ上部へ▲
▼17.流行性角結膜炎▼
咽頭結膜炎と同様にアデノウイルスの感染によって起こる急性結膜炎で、結膜炎の消退期に角膜炎を起こすことを特徴とします。最近のわが国では、アデノウイルス4型、8型が多く、その他3型、19型、37型、11型等によるものも増えてきています。
ページ上部へ▲
▼18.急性出血性結膜炎▼
エンテロウイルス70型の感染によって起こる急性結膜炎で、結膜下出血が高頻度に起こることを特徴とします。また、この病気はアポロ11号が打ち上げられた年(1969) にアフリカのガーナで初発したため、別名「アポロ熱」とも呼ばれています。わが国では1985年に沖縄全土に大流行したのが最初で、翌1986年にも再び流行が認められています。
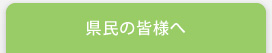
![]()














